07.23

お腹がすいた

お腹がすいた。
日本語でいうと、もともと満たされた胃袋があって、それが空になっていく感じがする。
喉がかわいた、も、もともとしっとりと潤った喉から、水分が蒸発していく感じが。
眠い、は、眠気を催す、眠気に襲われる、ともいうから、お腹がすいた、喉が渇いた、と同様、それは自分の意思では抗えないなにかであるように感じる。
英語の、I’m hungry、I’m thirsty、I am sleepy、も日本語に近くて、その状態であることは自分ではどうにもできないことであるかのように感じる。
しかし、イタリア語。
Ho fame、Ho sete、Ho sonno、は、直訳すると、「わたしは空腹をもっている」、「わたしは喉の渇きをもっている」、「わたしは眠気をもっている」で、つい視野が狭くなりがち、というより、広い視野などもったためしがなかったわたしには、衝撃的な発想の転換だった。
だって、「空腹」を「もっている」のだ。
「もっている」ことは、「もたないでいる」ことが対として存在する。
もつことも、もたいないことも、おなじように存在することとしての空腹。
いいえ、お腹がすいているときはお腹がすいているのであって、お腹がすいていないことにはならない、と、食べることが好きなわたしはこぶしを固く握りしめて主張しそうになるが、よく考えると、わたしが「お腹がすいた」と思っている「それ」は、はたしてほんとうの空腹なのだろうか。
空腹は、丸一日なにも食べなかったあたりから、空腹というよりにぶい痛みに感じるようになる。
そして、痛みは痛みであって、空腹ではない。
だから、ふだん、お腹がすいた、といっているときに感じているそれこそが空腹と呼ぶべきものだと思うのだが、でもそのとき、果たしてほんとうに食べたいかと問われると、必ずしも食べたいわけでもない気がする。
食べることも、食べないことも、選択することができることとしての空腹を、「お腹がすいた」といっている。
自分ではけっして抗えないと思ってきたなにか、は、ただの思い込みで、なんとかしようと思えば自分の意思でなんとでもできることだ。
その単純な事実に、「空腹をもっている」は気づかせた。
かつて、でたくてもでられない、もうどこにも行かれない、なにもできない、と思っていた。
なんでこんな目に遭わなければならないのだろうと人生を悲観したのは、でも、空腹とおなじようなものだった。
その出来事を通過させられたのは、人生は悲観と同様、希望を生きることを選べると、のちに確かに知るためだ。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








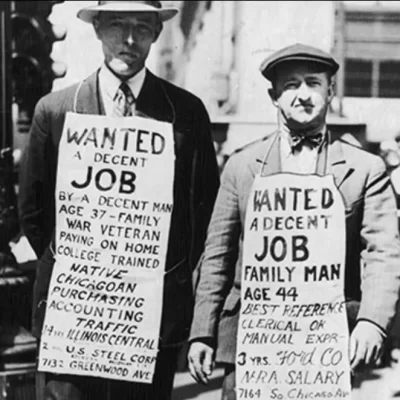
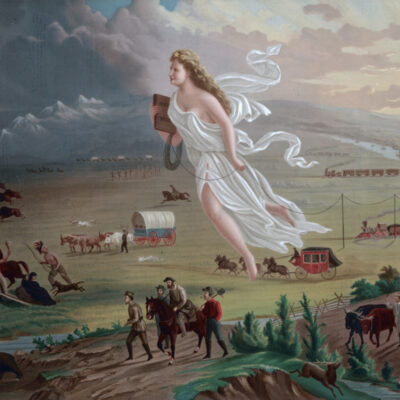







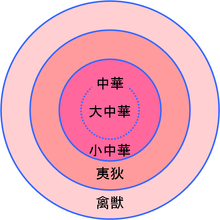
この記事へのコメントはありません。