07.28

失敗の効用

失敗した、と思うと動きが止まる。
このまま動きつづけて失敗を増やすより、じっとして失敗を増やさないことの方がまだましだと思うのだ。
でもふりかえると、失敗したと思った分、人生は豊かになってきた。
失敗とは、「方法がまずかったり情勢が悪かったりで、目的が達せられないこと」で、その説明文を見る限りでは、では方法を変えてみればよい、という考えに素直になる。
けれど、いざ現実で失敗したと思うことに直面したとき、方法を変えても取り返しがつかないと思うのは、だいたいにおいてそれが相手の感情と関わるからだ。
人がなにかを失敗と認識するとき、それは、でた結果が思っていたのとちがったときだ。
思っていたのとちがった結果というのは、たとえば、テストの点数がよくないとか、肉が生焼けだったとか、出来事としてはそういうこと。
でも、多くの場合それとセットなのは、そのことでだれかが怒ったり悲しんだりすることだ。
自分ひとりなら、あーあ、と思いながら、復習をしたり、もう一度火を入れて食べれば済む話も、他人の感情が関わると話はそれで済まなくなる。
そして人の感情というものは、概して基準などあってないようなものだ。
悪意がある人ならなおさら。
だから、失敗だと思ったとき、それはほんとうは変わらず成功につながる道を進んでいることなのに、その出来事がだれかの怒りや悲しみを引き起こしたことで、その取り組みそのものを失敗だと思い込んでしまう、それこそが失敗だったとふりかえって思う。
夫は理系で、「実験」をしてきたした人だ。だから失敗という概念がない。
「こうしたらこうなった、じゃあこうしたらどうなる? こうなるのでは? という仮説を立ててやってみる。でも結果は思っていたのとちがった。なるほど、こうなるのか、じゃあこうしたらどうなる? のくり返しだよ、実験は。で、データが少ないと質問に答えられないから、その方が研究者としてはまずいの。だから、思っていたのとちがう結果は、最終的には自分の研究結果が正しいことの裏付けにもなるから、最終的には役に立つことなんだよ」
食後のコーヒーを飲みながら、けんかをすることについても夫はそう考えているらしいことを思う。
けんかをするたびにもう終わりだと思うわたしと、そうではない夫。
これまでの人生で、けんかと仲直りが同じ数の人は、いまのところ夫だけだ。
「もっとも、研究結果が正しいというためにはお金を引っ張ってくる必要があって、そうすると、したい研究より、お金を引っ張ってこられる研究をするようになっていって、それでどんどんおかしくなっていくんだけど」
話が思わぬ方向にスライドするのも夫の特徴だけれど、その研究にお金をだすださないを決めるのも人の感情――表向きの理由はともかく――なのだから、そのことが社会を動かす一端になっているのはなんともあべこべなことだ。
そもそもなんの話だったっけ? と思う会話も、わたしたちが夫婦であることの裏付けになるといいと思う。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








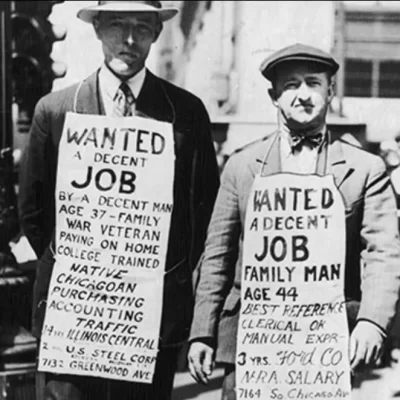
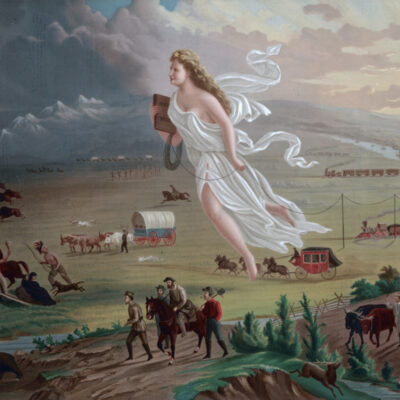







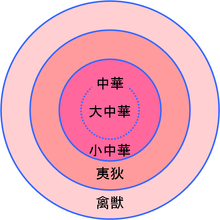
この記事へのコメントはありません。