07.30

景色

写真が好きだった。
学生の頃、使い捨てカメラや、フィルムカメラや、ポラロイドカメラで、とりとめないものばかり撮った。
父が亡くなったとき、遺品で一眼レフカメラをいくつかもらったが、どれも重すぎて使いこなせなかった。
いま手元にあるのは、片手でももてる軽量の一眼レフ。
使い勝手がいいというのはものをもつ上で大事なことだ。
雑誌、ともいえない紙の綴りを、友人たちとつくって回覧していたことがあった。
写真や絵や文章や、そのときどきにそれぞれからでてくるものを持ちよってつくっていた。
ひとりではできないことが数人集まればできるようになると知ったのはこのときで、こういうことを続けられたらいいなと思っていた。
けれど、やがて学生でなくなり、余裕のある時間がなくなり、友人たちと疎遠になり、紙の綴りもつくらなくなった。
ひとりではなにもできないと知ったのはこのときで、そのあと、ひとりでできることを探すようになった。
父は、撮った写真を何度もみる人だった。
紙に焼いたものもたくさんあったし、切ったフィルムに光を当てて壁に貼った白い紙に映しだしてみていた。
その紙が貼られていたのが父の部屋の扉だったから、中で写真が映しだされていることを知らずにうっかり扉を開けると怒られた。
なにをしても怒られて、カメラや写真の扱い方を教えてもらったこともないけれど、好きなことに熱中するのは父譲りのような気がする。
旅先で撮った写真をずっとみることがなかったのは、写真を撮るのは撮りたいからであって、撮った写真を見たいからではなかった。
大事なのは見ることではなく撮ることで、撮るのは見るためではなく残すためだと思っていた。
だから、撮ったものを見ることはかならずしも必要ではないと思っていたのだけれど、写真の整理をしていて思ったのは、見ることは残っていることを確認することだということだ。
残っていることを確認することは、それを撮ったのが自分だと確認することだ。
夢でも見ていたのではないかと思うほど遠い、でも美しくよいものとして記憶にある景色の写真は、自分がそこにいたから撮れたのであって、そこにいられたのは、自分がそこに行きたいと願い、そのために動いたからこそだ。
そのときのその人との関係は思うようにはならなくても、人は人を通じて自分に必要なことを得る。
ということを知るのが、その人との関係が終わってずいぶんあとになってからだとしても、望んではいなかったはずのその経験を通過したことでようやく見える景色があるのなら、すべて見えるものは、だれかから幸福に、満たされて生きてほしいと心から願われていることの証だと思う。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
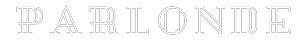







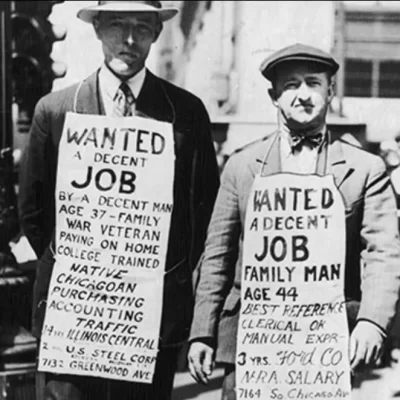
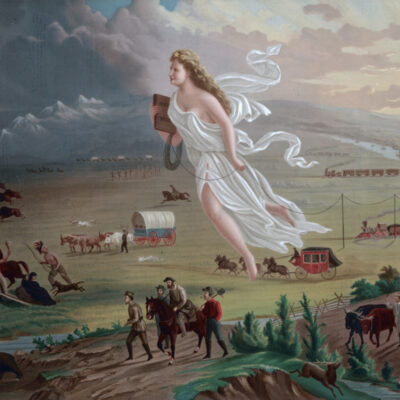







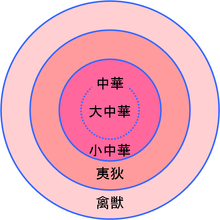
この記事へのコメントはありません。